こんにちは、はっちです。
今回、令和7年度電験1種二次試験(4回目(-_-;))を受験してきました。
このレポートも何度書けばよいのか、と思いながらもやっぱり記録として残しておこうかなと思っています。
管理人があたふたしながら受験している様子をご覧ください(ぇ)
冷静になってからの(?)全問題の難易度と感想をこちら。

試験前日はまず寝ることから難関
緊張と焦りから中々寝付けない前日。
回数を重ねれば若干楽になっているような気もしますが、性格的にあがってしまうのでしょう。
だからというわけではないのですが、試験前日は焦りと共に、眠れない・・・と思って睡眠アプリを入れてみました。
計測してみると、案外寝ていることが判明(何)
確かに起きている時間は長いけど、ちゃんと寝てました。自分が気が付いていないだけで。
朝のうちに変なことを安心しながら試験会場到着。
顔見知りがちょいちょいいるのが1種試験の面白いところ。みんなで早く突破したい(´・ω・)
そうこうしている内に試験監督が入室。
問題用紙が配られ、毎年の通り受験番号や試験地を書いていきますが、
突然。
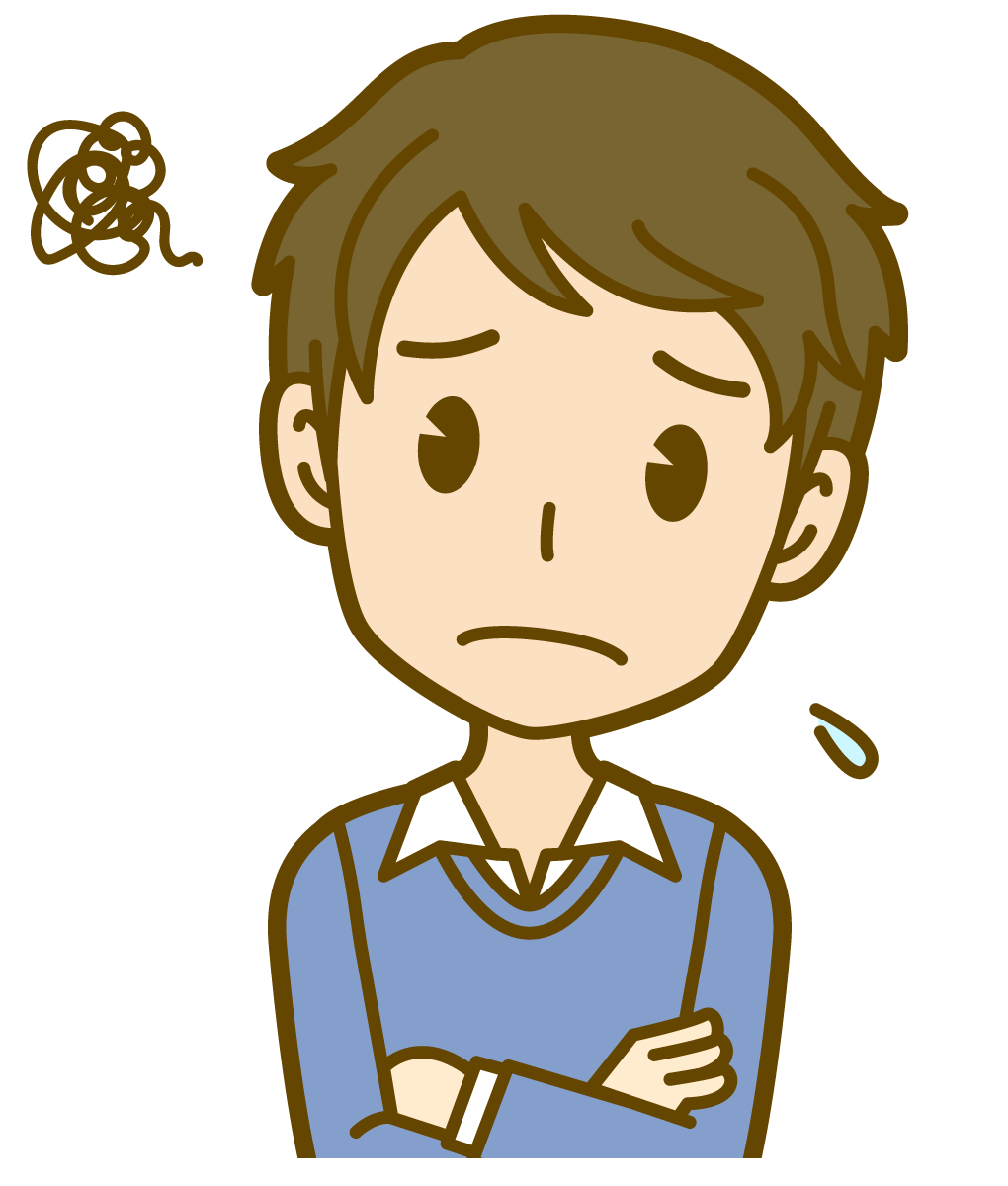
「いやいや違いますよ。」(@_@)ぇ?
急に教室中から上がる声。
なになに?と思っていたら、試験監督が試験地を間違えたらしい。
それに気が付く他の受験生。
まったく聞いてなかった自分(-_-;)
ふてくされてる試験監督(笑)
みんな落ち着いてますね。
そんなこんなで試験開始です。
まずは、すべての問題を見てどの問題で行くかアタリをつけます。

10:00 1時間目 電力管理試験開始
問1は予想通りの火力発電で安心。再熱サイクルのエントロピーの問題っぽい。
それほど難しくないのでは?これはアリか。
問2は、がいしの絶縁設計か。これもそこそこ書けそう。
154kV以上か以下か、塩害対策と汚損について書くことはたくさんありそうだけど、どれが正解なのか検証が必要そう。
問3は脱調に関するリレーの問題の様子。これは面白くて勉強した。系統的な話は好き。
問4は鉄塔の雷撃進行波の問題か。過去問であったな。これはいけそうだぞ。
問5・・・は?高圧の工事中の点検と年次点検について・・・
こんな問題1種で出すのか。
自分の実務にばっちり当てはまり、これはいけると判断するも問題を見て不安になる。
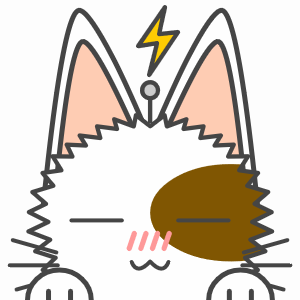
これもどれを書けばいいんだろう?
書けることが多すぎて、どれを書くのが出題者の求める答えなのか。
どれも正解なんだろうけど、本当にそうなのだろうか?
まぁでもアリ問題。次の問6を見て判断しよう。
問6は・・・まじか。速度調定率の問題だ。
こちらも過去問と似た問題な上にかなり易しい問題なので、もう1種試験では出題されることは無いだろうと思っていた。
これは選択すべき。。。と思ったら、こっそり論説入っていた。
ただこれも、正解の幅が広そう。どうしたものか。
全ての問題を確認、さぁどれを解く。
選択する問題を選ぶというところで、まずは問4雷撃鉄塔の計算問題で確実に点数を取りたい。
雷撃鉄塔とかなんかかっこいい。
そして問1の再熱火力。こっちも。。。(`・ω・´)サイネツカリョク!
問3の脱調分離リレーは仕組みが難しいけど何とか書けそうかな。
問2は書くことはたくさんあるが、出題者がどこを重視しているかが見えにくい。
後は問5か問6だが。。。断然問5のはずなのだが、色々気になる。
これは後で考えよう。
まずは問4の雷撃鉄塔問題から、と思ったら記述問題はここにもあった。
ただ、これは簡単。
さらっと計算問題に行き、間違えないように計算を進める。
全体像が見えているはずなのに、なぜか焦りで手が震えている。
この進行波の問題は分数が長くなってしまうのですが、分数の横線がまっすぐ引けない。
何度かやり直すけど、もういいやとぐにゃぐにゃの分数で記載。
思ったより落ち着けていない。
丁寧に計算して終了。以前に出題された過去問より簡単な問題でした。
続く問3の脱調分離リレー・・・かと思ったら(1)は脱調分離防止リレーじゃん。
まぁ、こちらも知っているから大丈夫。
続く(2)が脱調分離リレーの種類と仕組みでした。リレーの種類が明記してあるのは優しい感じ。
続いて問1の火力発電。
(1)がどの観点から書けばいいのか・・・と思いましたが、100字あるので、効率上昇の観点と、浸食の観点で記載。
(2)以降は、ただの入力と出力の問題でした。
開始45分で3問クリア。
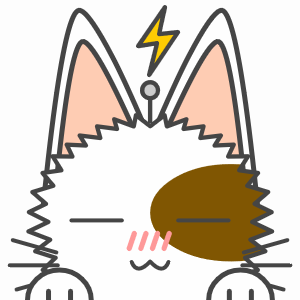
ふふん、いい感じじゃない・・・?
いや、このパターン。
2年前にもやった。そして余裕かました結果、
解ける問題を避けて高難易度の問題に挑戦して、結局今年も受験している。
油断してはいけない。
問5の高圧の検査点検の問題か。問6の給電指令と速度調定率の計算か。
間違いなく問5が有利。だけど何か引っかかる。
問6は速度調定率の問題が解けるかどうかだけ実際に解いて見て確認しよう。
・・・
解けた。
周波数変動大きいな!と思いながらも発電機の規模から妥当と判断。
もう半分の給電指令は項目は挙げられるが、”主要な指令”が何が主要なのか分からない。
需要家からしたら、需要家の開閉器操作指令は非常に重要な指令だけど。。。これはいいのか。
問5で気になるのは、何か法的な背景の記載が必要なのかどうか。
当たり前に使用前自主検査も年次点検も実施してきているので、そこの裏付けが薄い。
そんなことは求められていないけれども、模範解答がそこを背景に記述されると減点対象になりそう。
そもそも出題は高圧施設なので使用前自主検査(内容は似ているけど)じゃない。
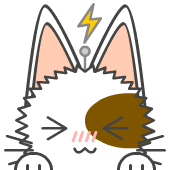
問6で確実に計算問題で半分取っていくのが正しいのでは?
やっぱり論説は怖い。他も取れているだろうし見えてる計算で15点を取りに行きたい。
その思いで問6を選択。思いっきりつられてる気もする( 一一)
前半の指令については、こんなのやるでしょ的に記載。
ただ、これも語句が正確でないといけない可能性もあり不安要素。
最悪0点でも計算問題は大丈夫と判断。
残り時間は1時間弱。
再度計算をやり直し、見直し完了。といっても計算問題少ないのですぐ終了。
後は恒例のきったない字をちまちま直して、試験終了まで選んでいない問2と問5の正答をなんとなく考えながら待ちます。
ちなみに試験終了後。
自分の職業を知っている人からすると、「問5を選んでいるに違いない。」と思われたためか、
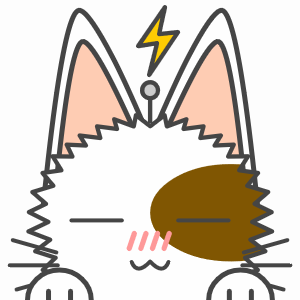
選ばなかったんですよ~あはは。
みたいな話をしたら、
「はぁ!?なんで!?」
「ありえない。」
「勇者だ(苦笑)」
など言われましたが、皆さん優しい冗談なのでちょっと心があたたまります。
何て言うんでしょうか。
せっかくなら勉強の成果を出したい。
そう思ってしまうんですよね。
試験終了後~お昼ご飯中
電力管理はかなり順調。機械制御は足切りである平均を超えさえすれば大丈夫では?
と思って臨んだ2年前は見事に落選。しつこい( 一一)
今年は、思い上がらずに全力で向かいます(心臓ばくばく)
この時間はお昼食べ終わってから特にすることないですよね。
一応論説がでるかも~ぐらいで拘束試験の測定方法について眺めていました。(出ませんでした)
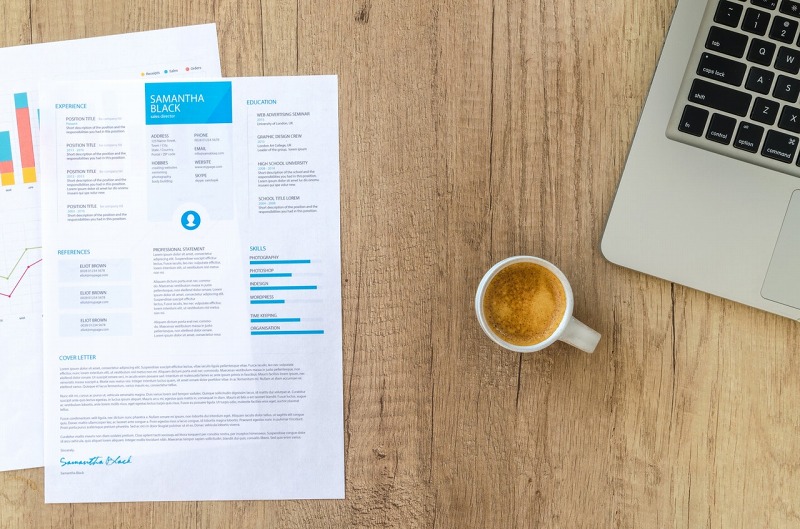
13:20 2時間目機械制御試験開始
制限時間1時間との勝負の機械制御。心のストレスがやばい。
とにもかくにも試験開始です。
まずは問を確認します。
問1:同期発電機のフェーザ図か・・・と思ったら抵抗成分がある。
よく見たら同期発電機では無く同期電動機じゃん。
後半の計算が大変そう。次を見てみよう。
問2:誘導電動機の問題だけど、去年に続きトルクの計算か。
これも道筋は建てられるだろうけど後半大変かも。
ただ問1よりも良さそう。候補1。
問3のパワエレはするーっと通過して自動制御の問4。
今度こそ現代制御では?と思ったらしっかり古典制御(*_*)
そして訳の分からない分離されたブロック線図。
もうナニコレ。
どうするどうする、と思いながらも見たことの無い問4からスタート。
ブロック線図の伝達関数でよくやるのは、最初にミスって全滅パターン。
これが無いように丁寧に計算・・・したくても心がそれを許してくれない。
相変わらず分数の横線はぐにゃぐにゃ。
20分後、分数に悪戦苦闘しながら最後までたどり着く。これ本当にあっているのだろうか。。。
続いて、問2の誘導電動機のトルクにチャレンジ。
(1)~(3)まではすんなり通過。数値のイメージも合いちょっと安心。
そして(4)。
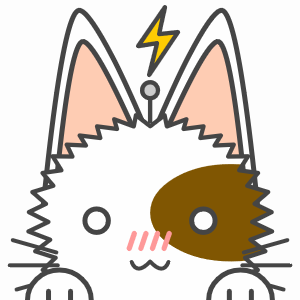
うげ、やっぱり計算がたいへんだコレ。
だけども、これが1種。
1種の問題からすると地獄の入口程度の計算量でしたが、やはり求めた数値は不安。
こういう複雑な数値の計算は大抵答えが当たらない。
一生懸命やっても、他の計算問題が心配なので、そっちを優先したい。
一応イメージ通りの滑りの値が出た。
もうこれでいいや。
そして、問4の伝達関数の間違いが無いか。滑りを含むトルク計算に間違いが無いかを再度確認。
良さそうだ。残り時間は10分。
汚い字を直しつつ、追記、注釈を入れつつ時間終了までもう少し。
すると。
隣「ぷっは~出た~」(小声)
終了寸前の1分前ぐらいに、隣から聞こえる声。
あぁ、この気持ちすごくよく分かる。それと同時に、この時間ぎりぎりまでやりきる精神力がすごい、と思う。
本当に機械制御は厳しい。濃縮された思いが伝わってくるよう。
そしてそのまま試験終了。
教室中に広がる終了の雰囲気。
終わった。
試験の余韻が残りつつも頭を休めようと試みます。
試験終了後の雑談会
恐らく機械制御もなんとかなったのではないでしょうか。
計算ミスがあったとしても後半だけで致命的にはならないはず。
帰り際、知り合い同士で軽く雑談しながら帰宅です。
「もう終わりたいですね。」
全員そんな気持ちだったかと思います。

令和7年度 電験1種二次試験 合格点予想
まずは合格予想点数ですが、ほぼ間違いなく108点でしょう。
電力管理において計算問題がほぼ過去問から似たようなものが出題されており、そこで点数が稼げた人が多かったのではないでしょうか。
ただ、全体から見ると計算問題の配点は、120点満点中のおそらく50点程度。
ですが、ここで稼げるというだけでとても重要です。
論説はやはり難しいところもありましたが、1種試験としては標準的ではないでしょうか。
また、機械制御も問1を除きそれほど難易度が高いとは思えません。
その問1も特別なことをしているわけではない・・・はず。
ですので二次試験の合格率は相当高くなるのではないかと思います。
もしかしたら、論説の採点を厳しくして若干の調整を図るかも?とか思ってしまいますが、そんな器用な調整を全受験者の採点にすることは難しいと思い直します。
今年は一次試験の合格率もかなり高くなっています。
総合合格率は10%を超えるかもしれません。
冷静な各問題については次の記事で。

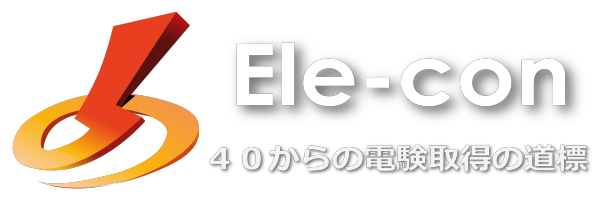



コメント