技術系で最高難易度と言われている技術士試験ですが、その難易度から、最高権威の資格とされ、その資格は博士号と同等とも言われています。
技術士試験を受験するけど、実際にどんな問題が出題されるのかな?という感じを知りたい方の参考になればと思います。
今回は二次試験についてです。一次試験の様子はこちら。

新方式技術士二次試験 試験の流れ
技術士の二次試験は令和元年度より新方式に変わり、すべて論文形式なりました。
それまでは択一式の問題が出題され、いろいろな分野からの出題と合わせて論文を作成するような形でしたが、新方式は論文のみです。表現力、構成力などの相手に伝える力が重視されているものと思われます。
詳細を見ていきたいと思います。
午前中に必須科目(2時間)
午後に選択科目(3時間半)
という試験構成でした。
感想としては、あまり緊張する試験でないにもかかわらず、非常に疲れました。
午前中の必須科目Ⅰ(試験時間2時間)

午前は必須科目ということで、電気電子分野を受験する人全員が同じ出題に対して論文を作成します。
出題は2題。
そのうちの1題を選び論文を作成します。
論文の制限字数は1800字(600字×3)を2時間で完成させる必要があります。
字数は上限しかありませんが、できるだけ埋めることが重要です。
内容を簡潔にまとめるのが大事な気がしますが、出題は非常に抽象的な形式を取ってきます。
令和3年度技術士二次試験電気電子部門より
このような出題形式のため、自分である程度テーマが決められる自由さがある反面、相当の知識が無ければ太刀打ち出来ない出題になっています。
そのため、
解答用紙が埋まらない→問題に対する電気電子技術の知識が少ない。
解答用紙を埋める→知識が豊富で書くスペースが足りない。
という捉え方をされ、それがそのまま採点につながっているのではないか?と言われているぐらいです。
ただそうなると、論文が中途半端になりかねないため、構成と文章量を見つつ、最後の(4)は文章量調整用の出題とも思えます。
こうなると試験時間2時間というのは、若干短いかもしれません。
悩みながら進めていると時間が足りなくなってしまいます。
午後の選択科目ⅡとⅢ(試験時間3時間半)

午後の試験も同様に論文試験になりますが、科目は受験申し込みをした時点で選んだ選択になります。
電気電子部門は、
電力・エネルギーシステム
電気応用
電子応用
情報通信
電気設備
の5項目に細分化されており、自分がどの分野を専門分野として受験するかによります。
電験を取得している人は比較的電力・エネルギーシステムが得意かと思われますが、
変電所の設計を行うに当たり、留意する点を述べよ。
など、実務に即した問題が出題されるため、素直に実務を理解している分野を選択するのが良いと思われます。
電気主任技術者として施設管理をしている人は電気設備の分野になるかなと思います。電気電子部門の中では電気設備で受験する人が一番多いです。
大問2つで3つの問題を解く(説く)

午後は大問Ⅱと大問Ⅲに分かれていますが、同じ時間内に解く必要があります。
大問Ⅱはさらに大問Ⅱ-1とⅡ-2に分かれており、Ⅱー1では、4つの設問が出題され、その中から1題選び論述します。
こちらは600字1枚が上限字数です。
一応4つから選択するのですが、私の選んだ電気設備分野では選べるものはほぼ1択。
電気設備は情報も電子も含まれるため、それらにも対応しているようですが、このため、電気設備分野が対象と思われる1つの設問以外、何を書けばいいのかわからないものばかりでした。(一応蓄電池の充電方法は書けたかも)
そして、中身の問題Ⅱ-1は完全に知識問題。
その電気設備部門の一例(簡略化)としては、
・高調波発生原因となるインバータの仕組みと、抑制対策を答えよ。
・蓄電池の停電に備えるために満充電を維持する充電方法について答えよ。
・屋外監視カメラに使用する主な撮像素子について、また撮像素子以外の監視システム構成技術について答えよ。
・低圧CVTケーブル幹線サイズの選定手順とECSOについての考えを述べよ。
など。(令和3年度技術士二次試験電気設備より)
知っていないと書けないものが出題されるため、4問という余地があって良かったなと思います。
勉強方法としては、電験2種の中でも施設管理系の論説問題を重視して勉強していくとよいかなと思います。
続く大問Ⅱー2は設備の更新や計画に関する問題が出題されます。
上限字数は1200字。
特定の工場などを背景にした出題が多く、工場の中でも半導体工場、また、病院、浄水場などいろいろな場面がその年によって設定されます。
それら建物の特性も踏まえて書くことができれば良いのですが、わからない場合想定するしかありません。
一方で、そういうところで働いていた経緯があれば。非常に有利な問題でもあります。
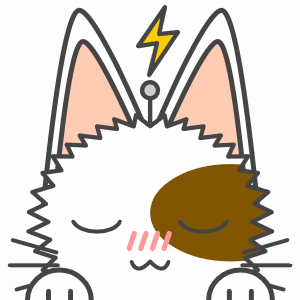
逆にその施設に務めていたりすると、当たり前だと思っていたことが課題だったりもするので良し悪しだとは思います。
Ⅱー2もまたそういう意味で個々による難易度の違いがありそうです。
そのためかⅡー2は出題が2題あり、そこから1題選択する形式です。
それでも実務と出題される分野が合致することは少ないでしょう。
技術士試験の難しさは、
どんな状況においても、幅広い電気電子の知識を持って問題に取り組む。
という能力が試されることかと思います。
大詰めの大問Ⅲ

続く同一時間内に含まれる大問Ⅲ。
こちらは、午前中の論文形式に近く、問題提起→課題抽出→波及効果と懸念
といった流れで問題が進みますが、新しい分野の技術をどう活かしていくか。というのが背景にありそうです。
こちらも技術を活かす方面についての「背景」が論文に設定されます。
その分野に精通していれば良いのですが、いかんせん何もわからない分野だと苦労します。
こちらの大問Ⅲもまた2題からの選択問題です。
出題形式はどちらも似ており、大問1と近い出題の仕方になります。
2問のうちどちらかが知っている分野に当たれば良いのですが、そうでない場合は想像で描くしかありません。
こちらは午前中と同じで制限字数(1800字)
知らない分野に新技術を適用する話をこれだけの量を書くのは、普通の勉強だけでは追いつかない気がします。
日頃から専門誌などを読みつつ、新しい技術のアンテナを貼りながら仕事をしていくことも、試験勉強につながります。
どんな問題が出題されるのかは予想が付きませんが、色々な知識を入れて置くことが大事です。
今回は電気電子部門の筆記試験の問題についてレポートでした。
次回は、この問題に対して実際に受験してみて、どういう過程で問題を解いていったかについて書いてみたいと思います。

それでは。
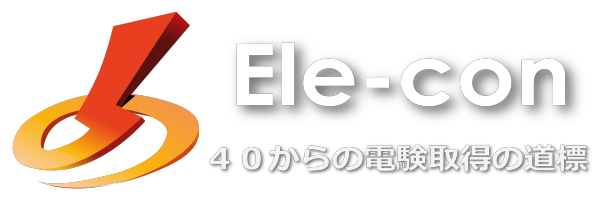




コメント